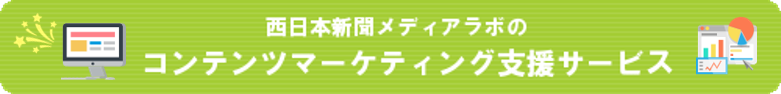メディアがファンを獲得するためにとる戦略とは

インターネットが浸透しきっている現代では、企業は消費者(ユーザー)から常に検索される側にいます。多くの企業はSEO対策を行うことで、自社メディアを検索エンジンの上位に表示させ、少しでもユーザーに見つけてもらう努力をします。しかしSEO対策は、あくまでもGoogleにおける検索結果で上位に表示されるための施策の一つにすぎません。自社メディアを安定して運営するためには、自社メディアのファンを増やすことが必要です。今回は、自社メディアのファンを獲得するために、コンテンツ制作担当者が押さえるべきポイントを紹介します。
ファンを獲得できるメディアは、どのような考え方を持っているのか

自社メディアを活性化させるためには、ユーザーの期待と情報への欲求を満たすコンテンツづくりを意識する必要があります。SEO対策を行って多くのユーザーを流入させたとしても、中身のないコンテンツであれば、ユーザーはファンになってくれません。それではユーザーを自社メディアのファンにし、何度も訪問してもらうためには、どのような視点が求められるのでしょうか? 今回は、多くのWebメディアやサービスの立ち上げを経験してきた『 ferret 』の編集長である飯髙 悠太さんに、自社メディアにファンをつくるためのポイントをお伺いしてきました。
ferret編集長 飯髙悠太さん

株式会社ベーシック Webマーケティング事業部 部長/ferret編集長。これまで広告代理店、制作会社、スタートアップを経験。複数のWebサービスやWebメディアの立ち上げに関わる。ferret立ち上げにあたり参画。
SEO対策だけで、メディアは生き残っていけない

SEO対策を行うことでWebメディアは、いくつかのメリットを得られます。その一つは、検索エンジンの上位に表示させることで、安定的にトラフィックを得られることです。
簡単に言うと、以前はサイトや記事に小手先の施策を実施すれば、検索結果の上位に表示させることが可能でした。しかし今のGoogleは、「その記事が、ユーザーにとって有益な情報なのか?」という点に重きを置いています。
なので、ユーザーが欲している情報と記事のマッチング性が高くなければ、検索結果の上位表示は難しくなるのです。自社メディアのユーザーがどういったキーワードを検索するのかを事前に考える必要があり、そのキーワードを検索するユーザーがどういった記事を欲しているのか、という観点が重要になります。
しかし、SEO対策だけしていても、永遠にPVが伸び続けるわけではありません。たしかに、SEO対策によって、ある程度のPVは伸びます。
しかし、次第に検索ボリュームの問題が発生します。検索ボリュームが出ないと、比例率で言えばPVは伸びません。メディアの特質上、新しいキーワードに対してはキーワードボリュームが伸びるケースもありますが、逆に縮小していくようなキーワードも存在します。PVが伸びるどころか下がってしまうケースも存在します。
たとえば「転職」などのキーワードのように、キーワードボリュームの変化が毎年あまりなく、ある特定の時期に伸び、他の時期にキーワードが伸びない市場もあります。その場合、単体のプロダクトとして考えると、PVは伸びていないことになります。
そこで、考えるべきは「SEO対策」ではなく、記事を読むことでユーザーがどのように喚起されるのか、課題がどのように解決されるのか、という「ユーザー視点」です。
メディアにとってSEO対策は、あくまでも自社メディアをユーザーに認知させるための手段となります。多くのコンテンツ制作担当者は、「コンテンツマーケティング」と「コンテンツSEO」の違いを理解できていません。前者はユーザーにとって自社メディアがどのように役立つのかを考えることであり、後者は検索結果の上位に自社メディアを表示させることを目的とした方法論です。
Googleが求めているのはユーザーにとっての有益な情報であるため、ユーザーに役立つ記事を出すこと自体がSEO対策となっていきます。
ファンのいるオウンドメディアが強い理由

これまで説明したとおり、WebメディアはSEO対策だけしていれば良いわけではありません。ユーザーを自社メディアのファンにさせることが必要です。
ひとくちに「ファン」と言っても、ファンとの接点はさまざまで、ファンごとに重み付けが異なります。たとえば、そのメディアが好きだからブックマークしてくれている人、FacebookやtwitterなどのSNSを通してファンになってくれている人、自社メディアの会員などです。
ファンはチャネルごとに存在し、自社とライトな関係なのかコアな関係なのかなどの「ファンの定義」を、メディアとしてルール化する必要があります。そして企業は、「ルールごとに、どのようなコミュニケーションを取る必要があるのか」を決定することが求められるのです。
ファンを会員として持っているメディアは、One-to-Oneのコミュニケーションを図ることができます。
たとえば、マーケティングオートメーションを導入している会社では、「会員登録」などの特定条件をトリガー(ある操作に対してあらかじめ指定した処理を起動する機能)として設定することで、ユーザーの行動を知ることができ、その結果、ユーザーに最適な記事を提供することが可能です。
たとえば、「SEOに関する記事」と「デザインに関する記事」を読むユーザーでは思考が異なります。そこでスコアリングを行い、重み付けを行います。
そして、メルマガを送るときは全会員に対して同じ内容で送るのではなく、それぞれのユーザーが求めている記事を知らせるような内容を送り、One-to-Oneのコミュニケーションを実現していきます。その結果、ユーザーがより自社メディアのファンになってくれるのです。
ファン獲得のために、どのようなことを意識するか

前述したとおり、自社メディアにファンをつくることで、ユーザーを安定して流入させることができます。それでは、ファンを獲得したいと考えたとき、どのようなことを意識すればよいのでしょうか。主なポイントは2つあります。
まず1つ目のポイントは、メディアを運用する目的を忘れないことです。多くの企業では、メディアを運用し、コンバージョンに結びつけることを目的としています。
とくに自社メディアを運用する場合に、KPI(重要業績評価指標)の指標が多くなります。コンテンツ制作担当者は多くのKPIを達成するため、PVを取ることに躍起になりがちです。その結果、ソーシャルメディアなどから爆発的にトラフィックを得るために「バズ」を狙うなどのケースが多々見受けられます。
確かにメディアである以上は、PVを得ることは重要な指標です。しかしながら、バズるのはあくまでも付加価値。バズることを目的とするのではなく、コンテンツが、読者にどう届くかに意識を向けていきます。そのために、目標のKPIを達成していく一方で、損益分岐点を設定するなどの工夫を行います。このとき、「どのようなタイミングでキャッシュを設けるのか」などのストーリーをつくる人が社内には必要となるでしょう。
またメディアを立ち上げる前に、メディア運営への期待値と、それに割けるリソースはあるのか、などを決めることが大切です。Webメディアを立ち上げようと考える企業は、「メディアをやれば儲かるだろう」と安易に考えがちです。
しかしWebメディアは、運営すれば簡単に利益が出るわけではありません。本気で取り組む覚悟がなければ、はじめから立ち上げない方が身のためです。
2つ目のポイントは、制作に関わる全員が「ユーザー視点」を持つことです。
ユーザー視点を忘れた記事では、興味関心を惹くようなタイトルを設定する反面、内容が薄くなる傾向にあります。ユーザーは、このような記事に満足してくれないばかりか、逆に不満を覚えてしまいます。また、ユーザー視点を忘れたデザインも問題です。
実際に、ユーザーのことを考えていないデザイン設計が行われてしまうことも多々あります。ユーザー視点を忘れないためにも、メディア運営に関わる全員に、想定するペルソナや自社のコンセプトを理解してもらうことが重要です。
その上で、「ユーザーの何を解決したいのか」「メディアとして何を達成するべきなのか」というKGI(最終目標達成指標)を、全員が共通認識として持ちましょう。このことは、全員の目線を合わせることにもつながるのです。そのあとに、目標を満たすKPIを決めていく必要があります。
まとめ
そもそもWeb上では、ユーザーと対面で話すことはできません。よって、不特定多数のユーザーと向き合うことが難しくなります。
メディアであるとより難しくなりますが、例えばそこでファン化を促し、One-to-Oneのコミュニケーションにつなげ、自社で想定しているユーザーの課題を解決できるようなコンテンツを配信していく必要があります。
これまでご紹介したとおり、自社メディアにファンをつくるためには、ユーザーベースでコンテンツに取り組む覚悟が必要です。