【サッカーマーケティング①】前年16位からJ1昇格したアビスパ福岡に学ぶ目標達成術
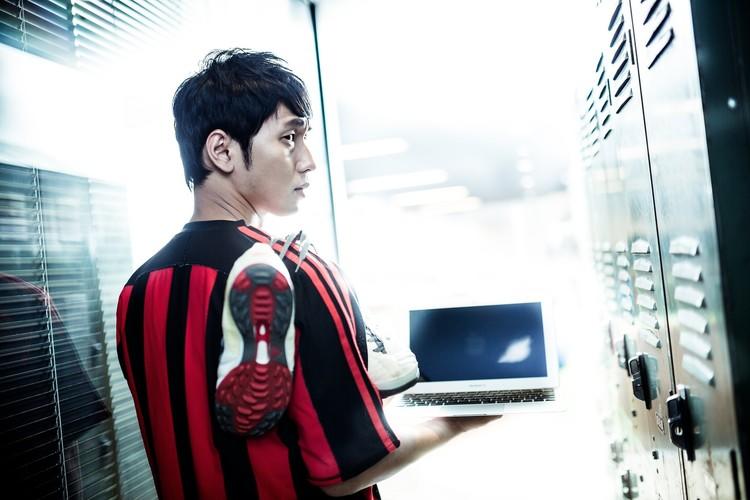
昨年サッカーJ2リーグにおいて、大旋風を巻き起こしJ1昇格を果たしたアビスパ福岡。 前年J2リーグ16位だったチームが、どのようにしてJ2史上最強の3位と言われるまでになったのでしょうか。 そこには、元日本代表で昨年から監督に就任した井原監督のマーケティング的な考え方があったのでした。
Jリーグは昇格と降格がある過酷なリーグ
Jリーグは、北は北海道から南は沖縄まで、全国で53クラブが加盟しています。
それぞれが、J1リーグをトップリーグとして、J2リーグ、J3リーグと3部のリーグに分かれて1年間戦います。
また、プロ野球と違い、年間の成績によって、それぞれのリーグ間でチームの入れ替えが行われます。
J1リーグにいるかどうかで、メディア露出やスポンサーフィーなどが大きく変わってくるので、
昇格と降格の間にいるチームは、優勝争いをしていなくても消化試合はなく最後まで気が抜けません。
昨年、アビスパ福岡が所属していたJ2リーグでは昇格の枠は3つ。
上位2チームが自動昇格となり、3位~6位の4チームがトーナメント方式で残り1つの枠を争います。
順位は気にしない!?組織を率いる監督が大切にしたこととは。

年頭に獲得に目標を聞くと、「10位以内」「2位以内」などと順位を挙げるのが一般的です。
しかし、アビスパ福岡の井原監督は、これまでの昇格したチームが獲得した勝点を調査し、自動昇格するための勝点目標を「76」と設定し公表しました。
これは、この勝点を取れば自動昇格できるから、他チームの動向は気にせず勝点を積み上げようというメッセージでもあります。
目標を達成するための期間は9ヶ月間。
これだけ長い期間モチベーションと保つのはプロの選手といえども、簡単なことではありません。
そこで、井原監督はリーグ戦42試合を6試合ごとに区切って、1クール毎の目標勝点を「11」に設定。
選手は、6試合ごとに目標との進捗確認を行うことができ、仮にその時点の目標を下回ったとしても、その差は明確なのでリカバリーの意欲も湧きモチベーションも保ちやすくなります。
マーケティング的目標設定を行った結果
上記のように、目標設定を行い、スタートしたアビスパ福岡でしたが、最初からうまく行ったわけではありませんでした。
開幕後まさかの3連敗スタートで最下位。過去に3連敗したチームが昇格した例はなく、傍からみると、「いきなりシーズン終了」と言ってもよい状況でした。
しかし、1クール(6試合)の目標勝点は「11」。残り3試合で3連勝すれば最大で勝点を9まで積むことができ、その場合の目標との差異はたった2です。頑張れば、その先で挽回できる範囲といえます。
結果は2勝1分で勝点7。目標との差異は-4。残り36試合で十分挽回できるところまで持ち直しました。
続く2クールでチームは快勝を続け、2クール終了時点で勝点は23。
目標とする勝点22を上回り、選手たちも自分たちのサッカーに対して自信を持てるようになりました。
その後、落ち込みをみせた場面もありましたが、目標の数字を達成すれば、自動昇格できると考えていたので、選手は他チームの同行を気にすることなく、目の前の試合で勝点をとることだけに集中することができました。
そして着実に勝点を積み上げ、最終的に目標を大幅に超える勝点82を獲得しました。
例年ですと自動昇格確実な数字だったはずなのですが、同じく勝点82を獲得したジュビロ磐田に得失点差でやぶれ3位となりました。
しかし、自信を積み上げてきたアビスパ福岡は、プレーオフで優勝しJ1昇格への切符を手にしたのでした。
まとめ
アビスパ福岡の昇格の裏にあるマーケティング的なポイントについてお伝えしましたが、
これは、ウェブでのマーケティングにも適用できると考えています。
ひとつめは、絶対的数字を目標にしたこと。
相対的な数字を目標にしてしまうと、自分たちがいくら頑張っても結果に結びつかないこともあります。
そうすると、相手ばかりを見てしまって本来やるべきことができずいつまでたっても本来の目標に届かないこともあります。
目標は、山に例えると山頂です。山頂を目指すルートは無数あり、どれを選んでも問題ありません。
迷った時は、山頂を見て修正が必要なら修正すればいいのです。
ふたつめは、目標数値を細分化し、短期目標を作ったこと。
目指す山は高いほうがいい。しかし、高過ぎるといつ到達するのかわからないので不安になります。
そこで、5合目、8合目などと短期的な目標地点を設置することで、目指すポイントが近くなりモチベーションを持続させることができます。
また、うまく行っていない時は次のポイントまでの修正案も作りやすいです。
ぜひ試してみてください。
