オウンドメディアには、何を書けばよいか。

インバウンドマーケティングを目的に、オウンドメディアやブログを始める企業が増えました。始めてから困るのが、記事のつくり方ではないでしょうか。どんな内容を、誰が、どの頻度で作成するのか。メディアごとの『決め』になってきますが、道標として「100万PVのブログ」運営者が行なっている方法を聞いてみました。
オウンドメディア・ブログ記事のつくりかた
いわゆる“オウンドメディア”が盛り上がっている。
検索エンジンなどからメディアにきた読者がファンになり、リピートして来てもらえれば非常にロイヤリティの高い顧客となってくれる可能性が高いからだ。そのため現在は「猫も杓子もオウンドメディア」とまでは行かないが、オウンドメディアを運営したい、という会社が多いのだろう。
だが、「定期的に良質な記事をアップするのは、非常に困難な仕事」だ。特に資金力のない中小、スタートアップ企業は記事を内製化せざるを得ないときも多いが、社内の人員に書いてもらうにも「何を書けばよいのか分からない」という現場の声は多いのではないだろうか。
特に最近では、単なる「まとめ記事」や「ライフハック系」の記事は読者が見飽きているため、質の高い記事をどのように継続的に作り上げていくのかは大きな課題だ。そこで今回は「オウンドメディアには何を書けばよいのか」を取り上げてみたい。
記事は大きく3種類
ざっくり言ってしまえば、「オウンドメディア」には3種類の記事しかない。
1. 役に立つ/後で読みたくなる記事
いわゆる、ライフハック、ノウハウ、商品・サービス紹介などの記事だ。
具体的なタイトルとしては「仕事がはかどる!8つのポイント」や、「これは行ってみたい!新橋のディープな焼肉屋が凄すぎた」など。
例えば私自信が執筆した記事としては、
「話のわかりやすい人」と「わかりにくい人」のちがい
尊敬する上司に教えてもらった、「仕事を任されたら何をすべきか」8箇条
などがあげられる
Webはどこからでもアクセスできるので、この手の記事はSNS、特に「はてブ」などで備忘録代わりに拡散されることが多い。また、この手の記事は検索されるキーワードを意図的に埋め込むことで、検索エンジンからの来訪者を招き、長く読まれることもある。まとめ記事やノウハウ系記事は比較的作るのが簡単なので、オウンドメディアの主役だ。
しかし逆にこの手の記事はどこのサイトも同じような記事になるため、今ひとつ「特定のファン」を生み出しにくい傾向にある。ターゲット層にロイヤリティを感じてもらいたい場合は、以下に紹介する「共感」や「一発芸」を記事に混ぜていく必要がある。
2. 共感する記事
「感動」や「いい話」に相当する記事を指す。感情には強いパワーがあるため、SNS経由で積極的に拡散され、時に大きなアクセスを稼ぐときもある。特に強いのはFacebookだ。しかし、検索エンジンには引っかかりづらいため、長期的な流入は見込みづらい。
例えば私自信が執筆した記事としては、
「なんで働かないといけないんですか?」と聞いた学生への、とある経営者の回答。
50歳以上しか採用しない会社の社長が言った、「人生の変え方」
などがあげられる。
- ノウハウ系⇒検索流入狙い
- 感動系⇒SNS経由の新規顧客狙い
また、「感動系」の話ばかりがメディアを埋め尽くしてしまうと、1つ1つの記事の重みが薄れるので、乱用してはいけない。感動系の記事は、文章で人の感情を動かさなくてはならず、書くのにテクニックが要るので、必要に応じて外部ライターに依頼するのも手だ。
3. 笑える記事/一発芸の記事
おもしろさ、驚きを提供する記事。具体的なタイトルは「いきなり~をやってみた」や、「びっくり!自分の目が信じられなくなる写真10選」、「思わずお茶吹いたシーンを挙げていく」など。
私自身はこのような記事は執筆していないが、「オモコロ」「ロケットニュース」などがこれに該当する。
上に紹介した1や2の記事は、価値観やその人の仕事のイメージ、知的レベルが反映されるため、共有が躊躇されるシーンもあるが3はほとんど躊躇なく共有される。いわゆる「万人向けコンテンツ」が多い。
したがって、「笑えるコンテンツ」や「驚きのシーン」ばかり集めているサイトは、上の記事よりも集客しやすいと言える。だが一発芸は、それを演じている人間へのロイヤリティを感じにくいため、アクセス数を稼いでも現実の仕事にはつながりづらい。編集によりうまくストーリーを作り、コンバージョンに繋げる工夫がいる。
オウンドメディアが目指す、ブランディングとコンバージョンに繋がるネタとは
オウンドメディアの目的は、ほとんどの場合がブランディングとコンバージョンである。メディア運営者の考え方や背景を発信することでブランディングし、顧客に興味を持ってもらう。そして商材やサービスを紹介することでコンバージョンに繋げるのだ。
したがって、書くべきネタは
- 「顧客となるべき人が読んで共感するか?」⇒ブランディング
- 「顧客となるべき人が役に立つ知識か?」⇒コンバージョン
の2つを主体にするべきである。
例えば結婚指輪を販売する会社のオウンドメディアは、以下のような記事を出していくと良い。
【共感】
・花嫁の感動ストーリー
・両親を大切にした話
・離れ離れの二人が苦難を乗り越えていく話
・マリッジブルーって何?
【役に立つ知識】
・結婚式までのチェックリスト
・結婚式までのスケジュール
・指輪の選び方
・指輪へのアンケート調査
逆にネガティブなこと(批判、中傷、他者を貶めること)は書かない。特に「批判」が好きな方は注意が必要だ。
ネタがなくなってくると、「こんな指輪は選んではいけない」「結婚式の失敗パターン」などのネタに頼りたくなる。創造的な記事よりも、批判する記事の方が簡単に作れるからだ。
しかし、批判はまず拡散されにくい。例えばFacebook上でいつもネガティブな人はブロックされてしまう。誰かを批判したり、不満を述べたりするネガティブな記事ばかり見ていると、疲れてしまうからだ。読者が記事を見たいのは、いい気分になりたいからである。
上の例で言えば、「指輪選びで大成功した人たちの意見」や「結婚式の成功のポイント」の方が、はるかに拡散されやすい良い記事である。ブランドを毀損しないためにも、注意していただきたい。
また、時として配慮のない記事が「炎上」を引き起こすこともある。これは違う意見をもつ人に配慮することが不足しているために起きることだ。そのため、「指輪を選ぶときはカラットの大きい物を選ぶ」などと断定する際には
「異なる考え方の人もいますが」
「全てではないですが」
という断り文句を必ず入れるか、もしくは何らかのエビデンスを入れること。断定的な物言いは好まれるが、それを尖らせすぎてしまうと、長期的なファン形成は難しい。
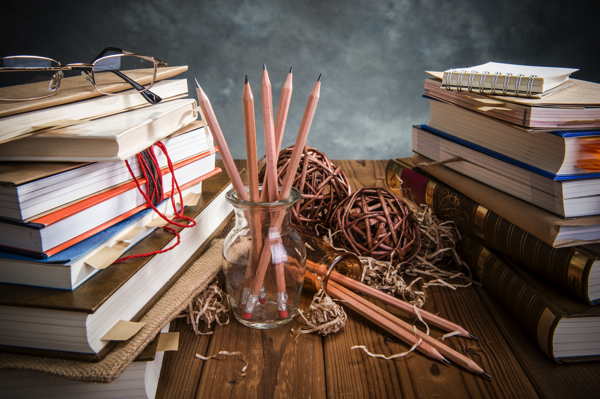
まとめ
もちろん、オウンドメディアはその企業のものであるから、”好きに書く”は本質である。だが、成果を出すことにフォーカスするならば、多少の工夫をすることは決して無駄ではない。
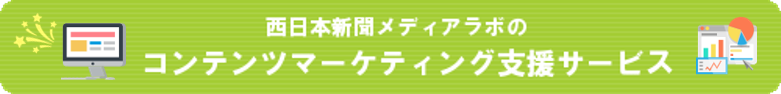
安達 裕哉、「オウンドメディアには、何を書けばよいか。」、SHAREBIZ、2015-12-24更新、http://www.lancers.jp/sharebiz/685、2016_06_27引用
